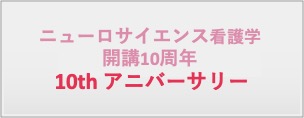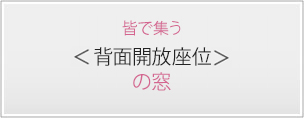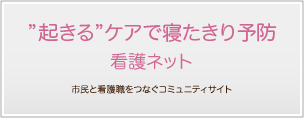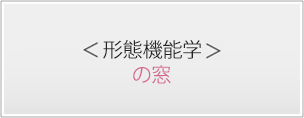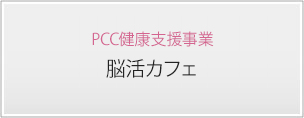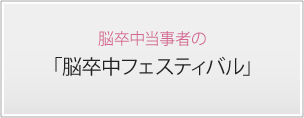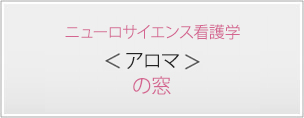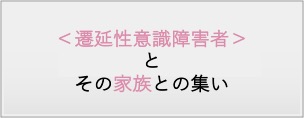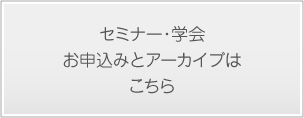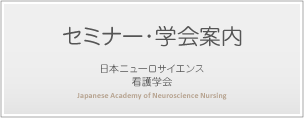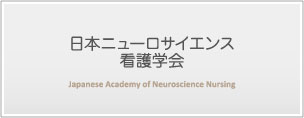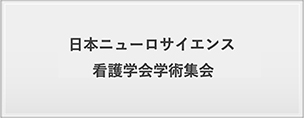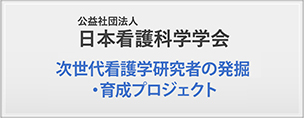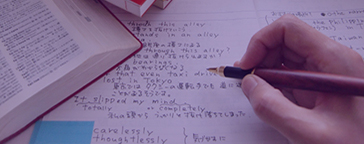活動紹介
ニューロサイエンス看護学は、2016年に聖路加国際大学大学院にて開講されました。同時にニューロサイエンス看護学研究会が発足し、いくつかの目的のために活動しています。
- 院生の研究において、より良い価値のある研究を生み出すために、研究計画から活動報告に至るまでお互いにディスカッションと意見交換を行う場としています。
- 修了生や有志を含めた全ての参加者が、ニューロサイエンス看護学を協働で学び合う機会となっています。研究者や専門看護師を始めとする各領域の専門家との連携をつくる機会にもなっています。
- ニューロサイエンス看護学という領域を深く広く発展させるために、研究室一丸となり、概念や定義の構築や研究の蓄積を目指しています。

在籍者は、教員と院生、修了生や聖路加国際病院を始めとした看護師やリハビリテーションのスタッフで構成されています。月に1回勉強会や特別講義を開き、学びを求める全てのメンバーが協力し合い研鑽を深めています。
研究活動
研究は脳神経科学に基づく脳神経疾患の看護ケアに主眼を置いていますが、各自の関心あるテーマを選択し科研費を取得して研究を進めています。
これまでの院生による研究内容に関しては修了論文一覧をご覧ください
当領域は、上級実践看護師コースと修士論文コースの二つを選択できます。テーマは院生によって様々で自己の研究課題は自由に選択することが可能です。研究対象も研究方法も、それぞれ異なりますが、適切な指導の下進めています。
教育活動
- ニューロサイエンス看護学の特論では、ニューロサイエンス看護学の基礎理論や基盤の知識を学習します。外部の有識者を招いたり、院生同士でプレゼンテーションなどがこの教育課程にあたります。
- 演習では、研究手法を身に付けるために、研究方法の学びや研究計画書に取り組みます。必要に応じて、医療施設や都外にてフィールドワークを行います。
- 実習においては、上級実践看護師に求められる臨床での技能と知識を実践に落とし込みます。実習場所も、自ら自由に選択して目標を達成できる施設を選択していきます。
- 脳神経を学ぶにあたって解剖生理学を学び直す研究室の院生は多くいます。自身の学習のために解剖実習に参加したり、より理解を深める目的で看護学部生の解剖生理学関連の講義アシスタント(ティーチングアシスタント制度)もすることができます。
社会貢献活動
- 脳神経看護ケアの質の向上を目的に、背面開放座位による勉強会を全国で開催しています。また、背面開放座位の普及と理解を広めるために、ガイドブックを作成しています。
- ニューロサイエンス看護学学会と連携し、脳神経看護に関する様々な看護ケアの研修を企画・開催しています。これまで多くの医療・福祉関係者が研修を受講しています。
- 看護系学会の理事会などを務めたり、病院機関や臨床看護師の方々の相談を引き受けています。
- ニューロサインエンス看護学を修了した看護師が、臨床で専門看護師として働いています。脳神経疾患を持つ患者と家族、地域の健康を考え、現場の最前線で看護を提供しています。
教授 大久保 暢子
脳神経科学研究を応用しながら、全人的に中枢神経系疾患患者の看護を追求する学問領域であり、脳卒中、頭部外傷、パーキンソン病などの神経変性疾患による意識・運動・感覚障害を持つ患者の看護を専門とします。科学研究を応用した先端技術の看護を追求する一方で、遷延性意識障害といった重症脳神経障害患者に焦点を当て、生命倫理やアドボカシーの観点からも学び、高度な実践ができる看護師およびエビデンスを創生する研究者を育成します。
研究・教育・社会活動を行う傍ら、プライベートでは夫と二人暮らしをしています。いつもどちらが家事をするかで議論し、ディベートの絶えない家庭でございます。仕事とプライベート、そしてエイジングとのバランスを考え、毎日を過ごしています。
院生に対しても勉学とプライベートとの両立を常に応援したいと思っています。

研究室の様子
教員、院生で日頃より演習室によく集まり、ディスカッションを行う中で、研究室一丸となって概念や定義の構築や研究を行っています。また、院生生活を送っていく中で、それぞれの課題やテーマが確立し、異なるテーマを追求していくことになりますが、それぞれの修士論文や課題研究に関すること話し合うことで、研究室みんなで課題解決しています。また、学年を超えても交流が深く、在院生のみでなく、修了生も定期的に研究会に参加してくれています。研究会は、月1回のペースですが、学内の院生のみではなく学外の看護系教員や大学院生も参加しています。学年や学内を超えてお互いに意見を述べ合い、お互いに助け合うことで院生も、教員も学び合いながら、ニューロサイエンス看護学の深く広い発展を目指しています。


助教 小林 由紀恵
2024年4月より、ニューロサイエンス看護学の助教として着任することになりました、小林由紀恵と申します。
わたしは、これまで急性期病院に勤務し、脳神経疾患を抱える患者さんやそのご家族に看護を提供してまいりました。
特に重篤な後遺症を有する方々が、住み慣れた場所で信頼できる人々と生活することが難しい状況に直面した場合に、彼らが望む生活を1日も早く取り戻せるよう、生活再構築に焦点を当てた看護に取り組んでまいりました。
大学院では、生活再構築の看護の一環として背面開放座位ケアに関する研究に取り組んでいます。
背面開放座位ケアを必要とする方々が公平にそのケアを受けられるよう、全国の医療施設や在宅で利用できる看護ケアプログラムの
構築に努めています。
今後、背面開放座位ケアの効果を検証し、脳神経疾患を抱える方々の生活の質を維持・向上ならびに脳神経疾患看護の質を高めるために、さらなる研究に取り組んでいく予定です。
脳神経疾患看護に興味をもつ皆様と共に、知識を深め、看護の発展に向けてともに前進していけることを楽しみにしています。

出版物のご案内
大久保暢子が、執筆・監修を担当した書籍を紹介します。
ベイツ診察法 第3版
メディカルサイエンスインターナショナル 2022年9月
詳細を見る
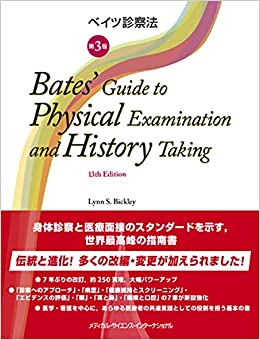
新体系 看護学全書 人体の構造と機能➌ 形態機能学
株式会社メヂカルフレンド社 2022年2月
詳細を見る

フィジカルアセスメント ポケットBOOK 項目ごとに正常かどうか判断しよう
照林社 2020年12月
詳細を見る
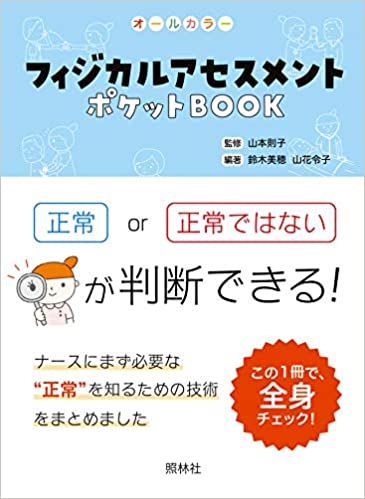
日常生活行動からみるヘルスアセスメント―看護形態機能学の枠組みを用いて
日本看護協会出版社 2016年8月
ヘルスアセスメントを「食べる」「動く」「トイレに行く」などの日常生活行動の視点から構築した書籍である。通常はフィジカルアセスメントとして循環器系、呼吸器系などの系統別にアセスメントの知識や技術を学習するが、この書籍では、看護が臨床現場で行っている日常生活行動の援助の視点からフィジカルアセスメント、心理的側面、社会的側面をアセスメントし、看護ケアに繋げる書籍である。
詳細を見る
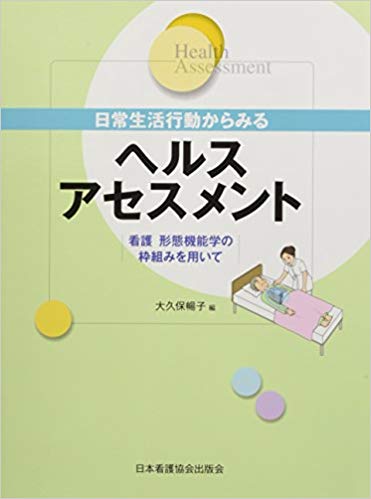
ヒューマンボディ原著第5版 からだがわかる解剖生理学
エルゼビア・ジャパン株式会社 2017年12月
詳細を見る

見て知るリハビリテーション看護 脳卒中急性期のリハビリテーション看護
丸善出版 2016年1月
詳細を見る

フィジカルアセスメントがみえる
メディックメディア 2015年4月
詳細を見る
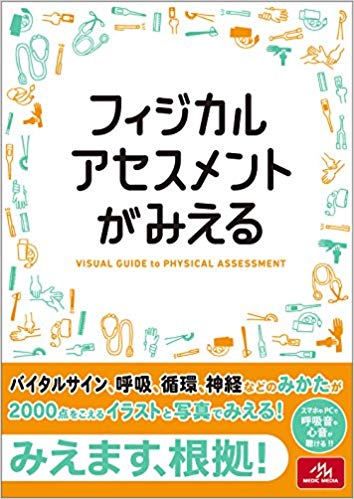
なるにはBooks 大学学部調べ 看護学部・保健医療学部
2章:教員インタビュー、3章:看護学部・保健医療学部のキャンパスライフを教えてください
ぺりかん社 2017年4月
詳細を見る
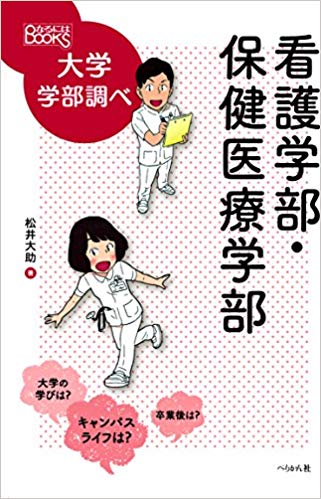
その他の出版物に関しては、大久保暢子のデータベースをご覧ください。
ニューロサイエンス看護学を学びたい方
本研究会の修士課程、もしくは博士課程に入学希望の方々は、本大学院の入試サイトにて詳細をご確認ください。
進学を希望されている方へ
本研究会の修士課程、もしくは博士課程に入学希望の方々は、本大学院の入試サイトにて詳細をご確認ください。